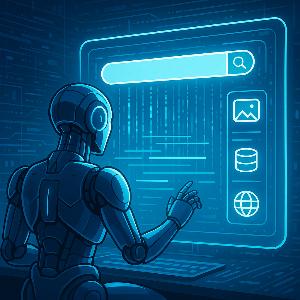Google の「AIモード(AI Mode)」検索が開始されました。概要は以下のとおりです。
Google AIモードとは何か
「複雑な質問を、一度で聞いて、それに対する“まとまった答え”をGoogleが生成AI(Gemini)で返してくれる検索モード」です。従来の「検索 → リンクをいくつか開く →内容を比較する」という手間を省いて、「要点をまとめて教えて →必要なら詳しいリンクも示す」方式。 無料です。
特徴として:
- 長め・複雑な問いや背景を含んだ質問を受け付ける。複数のサブトピックに分けて調べる。
- テキスト・音声・画像入力など複数手段で質問できる。 (Google サポート)
- フォローアップ質問が可能で、対話形式で深掘りできる。 (Google サポート)
使い方(ステップバイステップ)
中小企業の経営者でもすぐ使えるよう、スマホ中心のパターンで:
- Googleアプリを開くか、ブラウザで google.com を開く。
- 検索バーのそばに「AIモード」あるいは「AI Mode」タブがあればそれをタップ/切り替える。従来検索タブと並んで表示される。
- 質問を入力(テキスト)、または音声/画像を使う。たとえば「来月福岡近辺で社員研修に良さそうな宿と交通アクセスを含めて3案教えて」など。
- AIの回答を見る。要点のまとめがまずあり、その下に参照元のリンクが出ることが多い。必要ならリンク先で詳細を確認。
- フォローアップ:回答に「もっと細かく教えて」「コスト優先で」「交通便利さ重視で」など条件を足して再質問。対話形式でさらに絞ることができる。
※最初はこのモードが自分のアカウント・デバイスで使えるか確認が必要(国、アプリ/ブラウザのバージョンなどで順次提供中)。
中小企業・働く人にとってのメリット
モチベーションや効率を上げる観点で、こういう良い面があります:
- 意思決定のスピードアップ
例:仕入れ先を選ぶ際「この品質・価格・納期の組み合わせならどこがいいか?」とAIモードで尋ねれば、複数の候補を比較検討し説明してくれる。これまでは自分でサイトを何社も見て比較する手間があったが、AIモードで短時間で方向性が見える。 - 情報の見落としを減らす
複数の情報源をAIが取りまとめてくれるので、「重要な条件を忘れていた」ということが減り、提案・判断の精度が上がる。たとえば新製品の導入を検討する際に、コスト・導入後のメンテナンス・対応サポート・評判など複数角度から短時間で情報を得られる。 - 教育・研修で使いやすい
新人教育の準備などで、「この分野の基礎」「業界の最新トレンド」をまとめて教える資料を作るのに使える。教える側の準備時間が削減でき、その分、教える内容の質を上げたり、個々のフォロー時間に回せる。 - 顧客対応や企画立案がスマートに
社内・顧客から来る複雑な問い合わせに対して、まずAIモードで背景を整理し、複数案を持って会議できる。たとえば「顧客の新しい要望をどう満たすか」などで複数案を準備でき、会話の質が上がる。
注意点・リスク・影響(会社として押さえておくべきこと)
ただし良い面だけではありません。注意しないと逆効果になることもあるので、経営者として把握しておきたい影響を整理します。
| リスク/影響 | 具体内容 | 対策・注意すること |
|---|---|---|
| ウェブサイトへの流入減少(ゼロクリック増加) | AIモードで回答を与えた段階で満足してしまい、リンクをクリックしない「ゼロクリック検索」が増える。サイト運営者・ネット集客をしている企業には死活問題に。 | 自社ブランドがAIの回答に含まれるよう情報発信を強化する。FAQ・比較コンテンツ・独自性のあるデータや見解を持つページを作る。SEOだけでなく「AI最適化(AIO)」も検討する。 |
| 正確性・信頼性の問題 | AIがまとめる情報に誤りが混じる可能性がある。引用元リンクをチェックしないと誤った判断をすることも。 | 特に重要な判断に使うときは複数の情報源で裏を取る。社内で「AIの草案」として扱って最終チェックする人を決める。 |
| パーソナライズ/プライバシーの配慮 | 過去の検索履歴・設定に応じてパーソナライズされた結果が出ることがあり、一般的な情報とは少し異なる可能性。 | 社用アカウントと個人アカウントを使い分ける、社内共有の場合はできるだけ中立的なアカウントで情報収集する。 |
| 競争環境の変化 | 他社もこのツールを使い始めたら、情報発信の速さや内容の質が差となる。AIモードで先に回答に出る企業が有利になる。 | 情報発信・コンテンツ作成を早める、独自性/地域性・顧客の声など「オンリーワン」の内容を持たせる。社員にも使い方を教育する。 |
| 過信による判断ミス | 「AIがこう言ってるから‥」とチェックを怠ることは速度は出るが誤りの原因に。例:法律・労務・契約など重大な分野では専門家の確認が必要。 | AIを補助ツールと位置付け、最終判断は人間がする。専門分野では専門家の意見を取り入れる体制を整える。 |
AIOの具体的な方法
(1) FAQ形式でコンテンツを作る
- AIは「質問→答え」という形式に強い。
- 自社サイトに「よくある質問(FAQ)」を充実させ、専門的なQ&Aを公開する。
→ 例:「中小製造業がISO認証を取るときの手順は?」「小売店の人手不足対策の実例は?」など。
(2) 事例・データを公開する
- AIは「具体例」「統計」「ケーススタディ」を回答に取り込みやすい。
- 自社の顧客事例、改善データ、数字を伴った成功事例を積極的に発信する。
→ 「〇〇市の製造業で残業削減20%成功」など。
(3) 信頼性を担保する発信
- 発信者情報(著者名・資格・経歴)を明記する。
- 引用されやすい一次情報を出す(オリジナル調査、業界の最新動向まとめなど)。
- GoogleやAIは「信頼できる専門家の情報」を優先する傾向が強い。
(4) 多様なフォーマットで出す
- テキストだけでなく、画像・動画・インフォグラフィックなども有効。
- AIが解析できるのはテキスト中心だが、ユーザーの滞在時間・共有率を高めることで「参照価値の高いサイト」と認識される。
(5) 構造化データ(Schema Markup)の活用
- 製品情報・住所・レビューなどをマークアップしておくと、AIや検索エンジンに正しく理解されやすい。特に「店舗・イベント・商品」の情報はSchemaを使うとAIの回答に組み込まれやすい。
Schemaとは?⇒検索エンジンやAIに向けた「説明書き」。普通の人が読む文章は「自然文」ですが、検索エンジンは意味を理解しづらい。そこで「これは会社名ですよ」「これは住所です」「これは商品のレビューです」といった構造化データ(structured data) をHTMLに埋め込むと、検索エンジンやAIが理解しやすくなります。
具体例
例え話を交えて:
例え話:レストランのメニューを増やすかどうか考え中の店長
店長が「季節限定メニューを作ろうか?コスト・材料仕入れ・お客さんウケ・売値設定・宣伝方法まで含めて3案教えて」とAIモードに聞くと、AIは材料コスト比較、似た業態での成功例、売価シミュレーション、宣伝チャネルの提案などを一発でまとめてくれる。これにより、店長は自分で食材店を調べたり、似た店に聞きに行く手間が省け、その分「お客さんの声を聞く」など別の創造的な仕事に時間を使える。
例:製造業の社長が人手不足対策を考える
「パートと正社員の混合勤務制度を導入した場合のメリット・デメリット」「採用コスト・教育コスト・モチベーション維持方法」などをAIモードで整理してもらう。対策案ごとのコスト比較まで含めてくれれば、検討会議がすぐにできる。
経営者として今やるべきアクション
影響を前向きに取り込むために、具体的にできることをいくつか提案します:
- 情報発信強化(ブランドを見える形にする)
自社サイト、ブログ、SNSなどで、業界特有の知見・成功事例を発信し、「この分野ならこの会社」という話がAIの回答にも含まれるようにしておく。 - コンテンツの質と独自性の確保
他社との差別化ポイントを明確にし、それを伝えるコンテンツを持つ。単なる情報のまとめではなく、「体験」「事例」「ノウハウ」「顧客の声」などを加える。 - 社員教育/ツール導入
従業員がAIモードや類似ツールを理解・使えるようにし、リサーチ業務・企画業務の効率を上げる。定期的に共有会などで良い使い方・失敗例を持ち寄る。 - チェック体制の構築
AIが出してきた案・数字をそのまま使うのではなく、社内で確認するプロセスを設ける。特に法務・労務・安全などリスクのあるところは慎重に。 - マーケティング戦略の見直し
従来のSEO中心・広告依存の方法だけでなく、AIモードで「回答に含まれること」を狙うコンテンツ設計を考える。例えば「よくある質問」形式で、自社が答えの中に引用されやすい形を整備する。
将来の見通し
- 「ゼロクリック」がさらに増える可能性が高い。ユーザーがすぐ答えを得てしまうため。これにより、ウェブサイトへの訪問者数が減る業種が出るかもしれない。
- 検索クエリの“言葉”から“意味・意図”への移行が進む。キーワードの数や形式より、「何を知りたいか」「どういう視点か」が重要になる。
- 広告モデルやSEOのやり方が変化する。たとえばAIモード内の回答にも広告が混ざる可能性、AI回答に評価されるコンテンツの基準が変わる可能性あり。