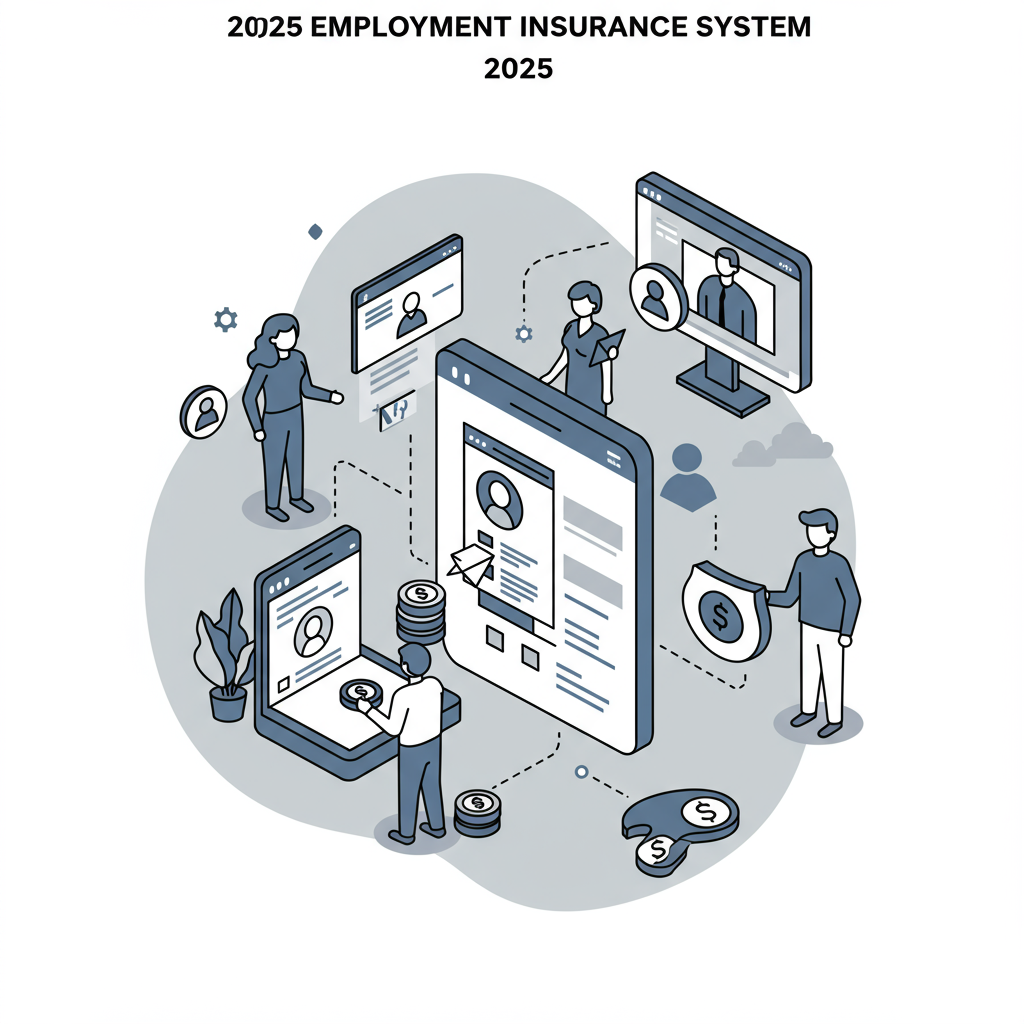以下、労働・社会保険業務研修会での内容です。社会保険労務士向けの研修会でしたが、中小企業の方も関係する部分が多いので是非とも、参考にしてください。尚、抜粋ですので、詳細な内容は各省庁等のホームページ等をご確認ください。
今回の改正は、労働者のキャリア形成支援と、少子化対策として子育て支援を強化し、男女ともに育児を担える環境を整備することを目的としています。
雇用保険制度改正の主な変更点と注意点
今回の改正は、2024年4月1日、2024年10月1日、2025年4月1日、2028年10月1日と段階的に実施されます。
1. 教育訓練給付金の給付率拡充
対象期間と給付率の変更
- 2024年9月30日までに訓練を開始した方
- 訓練費用の50%を支給(年間上限40万円)。
- 資格取得・就職した場合は、さらに20%(年間上限16万円)を追加支給。
- 2024年10月1日以降に訓練を開始した方
- 上記の50%(+20%)に加えて、訓練終了後の賃金が訓練開始前より5%以上上がった場合、さらに10%(年間上限8万円)を追加支給。
- 合計で最大80%の給付が可能になります。
注意点
- 賃金上昇の比較方法が変わります:離職者と在職者で賃金比較の期間や算出方法が異なります。
- 離職者:訓練開始時の離職直前6ヶ月間の賃金日額と、訓練終了後、就職から1年以内の任意の連続する6ヶ月間の賃金日額を比較します。
- 在職者:訓練開始日前の直前6ヶ月間の賃金日額と、訓練終了後、資格取得から1年以内の任意の連続する6ヶ月間の賃金日額を比較します。
- 賃金上昇による追加支給を受けるには、ハローワークへの書類提出と確認が必要です。
2. 特定一般教育訓練給付金の給付率拡充
対象期間と給付率の変更
- 2024年9月30日までに訓練を開始した方
- 訓練費用の40%を支給(年間上限20万円)。追加支給はありませんでした。
- 2024年10月1日以降に訓練を開始した方
- 上記の40%に加えて、資格取得・就職した場合、さらに10%(年間上限5万円)を追加支給。
- 合計で最大50%の給付が可能になります。
3. 自己都合離職の場合の給付制限期間の短縮(2025年4月1日以降)
変更点
- 原則2ヶ月から1ヶ月へ短縮:2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、基本手当が支給されない期間(給付制限)が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。
- 例外:過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合や、会社都合による重責解雇の場合は、給付制限が3ヶ月となります(これは変更ありません)。
教育訓練を受けた場合の給付制限解除
- 離職前1年以内に教育訓練を受けていた場合:給付制限が解除され、待期期間(7日間)終了後すぐに基本手当の支給対象となります。
- 受給資格決定後に教育訓練を開始した場合:教育訓練の開始日以降、給付制限が解除され、基本手当の支給対象となります。
注意点
- 給付制限が解除される教育訓練は、以下のいずれかに該当するものに限られます。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 職業安定局長が定める訓練
4. 就業促進手当の廃止と就業促進定着手当の給付率引き下げ(2025年4月1日以降)
就業促進手当の廃止
- 2025年度末をもって就業促進手当が廃止されます。
就業促進定着手当の給付率引き下げ
- 2025年4月1日以降に再就職手当の支給にかかる再就職をした方
- これまでの支給残日数の40%または30%(上限あり)から、一律20%に引き下げられます。
- 就業促進定着手当とは:再就職手当の支給を受けた方が、再就職先で6ヶ月以上雇用され、再就職先の6ヶ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給されるものです。
5. 高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ(2024年4月1日以降)
変更点
- 賃金が60歳到達時点の75%未満に低下した場合に支給される高年齢雇用継続給付の支給率が、引き下げられました。
- 具体的な変更:
- これまで:賃金の低下率が61%以下の場合、支給率15%
- 今回から:賃金の低下率が64%以下の場合、支給率10%
- これにより、給付される金額が減少します。
注意点
- 今回の改正は、2024年4月1日以降に支払われた賃金に基づいて適用されます。
6. 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの厳格化(2024年4月1日以降)
育児休業給付金の延長について、保育所に入所できなかった場合の取り扱いが厳しくなりました。これは、制度の趣旨に沿った適正な運用を目的としています。
主な変更点
- 書類の追加:
- 「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
- 市町村に提出した保育所等の利用申し込み書の写し(全ページ)
- 「入所保留通知書」などの自治体発行の利用不可通知書(これはこれまで通り必要)
延長の要件(これら全てを満たす必要があります)
- あらかじめ市町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 子の1歳の誕生日(誕生日の前日)までの日付で入所を申し込んでいる必要があります。
- 単に申し込みを忘れていた場合や、市町村への問い合わせで「入所は困難」と言われただけで申し込まなかった場合は、延長が認められません。
- ただし、子の病気や障害で特別な配慮が必要な場合など、やむを得ない事情がある場合は、医師の診断書などを添付することで認められることがあります。
- 速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望しているとハローワークが認めること
- 原則として、子の誕生日前日までの日を入所希望日として申し込んでいること。
- 自宅から片道30分以上かかる施設のみに申し込んでいないこと(ただし、以下の合理的な理由がある場合は例外)
- 通勤経路の途中にある。
- 自宅から30分未満で通える保育所がない。
- 30分未満で通える保育所の開所時間・開所日が、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない。
- 子の病気や障害により、30分未満で通える保育所では受け入れができない。
- 入所保留となることを希望する意思表示をしていないこと:延長したいがために、わざと遠い施設を希望したり、「入所を希望しない」という意思表示をしたりしていた場合は、要件を満たしません。
- 子の1歳の誕生日(誕生日の翌日)時点で保育所の利用が見込めないこと
- 市町村が発行する「入所保留通知書」の提出が必要です。
- 通知書の発行年月日が、子の誕生日の翌日の2ヶ月前(4月入所の場合は3ヶ月前)以降の日付であること。
- または、それ以前の通知書の場合でも、通知書の保留有効期間が子の誕生日を含んでいる場合に有効と見なされます。
注意点
- 厳格化ではなく適正化:今回の改正は、あくまで育児休業給付金制度の適正な運用を目的としています。
- 不正受給に注意:提出された申し込み書の内容が実際の申し込み内容と異なる場合、不正受給と見なされる可能性があります。
- 申請書類の確認:ハローワークで市町村への申し込み内容を確認する場合があります。
7. 出生後休業支援給付金の創設(2025年4月1日以降)
目的
- 共働き・共育てを推進するため、特に男性の育児休業取得を促進することが目的です。
給付内容
- 出産直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間支給されます。
- 通常の出生時育児休業給付金や育児休業給付金に上乗せして支給されます。
- 支給額は、休業開始時賃金日額の**13%**です。
- この給付金と育児休業給付金を合わせると、手取りで在職中とほぼ同額になるよう設計されています。
支給要件
- 被保険者(給付金を受ける方)の要件:
- 対象期間に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を、通算して14日以上取得したこと。
- 父親の場合の対象期間:出産日または出産予定日のうち早い日から、出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日まで。
- 母親の場合の対象期間:出産日または出産予定日のうち早い日から、出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日まで(産後休業期間を含む)。
- 被保険者の配偶者の要件:
- 出産日または出産予定日のうち早い日から、出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に、通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
- または、以下のいずれかの理由で配偶者の育児休業を要件としない場合に該当すること。
- 配偶者がいない
- 配偶者が子の法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け、別居している
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営やフリーランスなど、雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中である
- その他の理由(詳細はハローワークで確認)
注意点
- 配偶者の育児休業を要件としない場合は、申請書にその理由を記載する必要があります。
- 男性の育児休業取得を強力に後押しする制度です。
8. 育児時短就業給付金の創設(2025年4月1日以降)
目的
- 仕事と育児の両立支援のため、育児中の柔軟な働き方(時短勤務)を選択しやすくすることを目的としています。
給付内容
- 2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合で、育児時短就業前の賃金と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に支給されます。
- 支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。
- 支給される期間は、育児時短就業を開始した月から、育児時短就業を終了した月までの各暦月です。
支給要件
- 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること。
支給されないケース(不支給)
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していない時(100%以上の場合)。
- 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額(2025年7月31日までは459,000円)以上である時。
- 支給額が最低限度額(2025年7月31日までは2,295円)以下である時。
経過措置
- 2025年4月1日以前から時短就業している方でも、要件を満たせば2025年4月1日以降の期間について支給対象となります。
注意点
- 時短勤務で賃金が低下した場合の生活を支えるための制度です。
- 申請は原則2ヶ月ごとに行いますが、希望すれば1ヶ月ごとの申請も可能です。
今回の制度改正は、多様な働き方を支援し、子育てと仕事の両立を促進するための重要な変更です。制度内容が複雑な部分もありますので、ご不明な点があれば、事業所を管轄するハローワークへお問い合わせください。