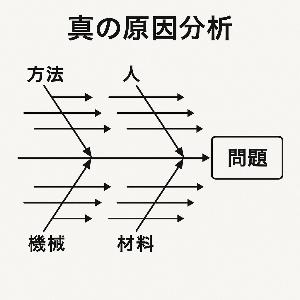石井力重氏著の「ビジネススキルAIを使って考えるための全技術」より。
AIで「賢く」解決策を見つける方法 💡
AIに解決策を直接尋ねるのではなく、
何が解決を妨げているのかを尋ねるのがより賢い方法です 。こうすることで、直接的な解決策では見えなかった、問題の根っこにある原因を特定できます。この方法は、「阻害の要因」という技法で、著書『AIを使って考えるための全技術』で紹介されています 。これは、創造工学の「何があなたを制止するのか」という分析手法を応用したものです 。
「阻害の要因」テクニックの使い方
この方法は、たった2つのステップで実行できます。
- 正しい質問をする: 適切なプロンプト(AIへの指示文)を使って、問題の障害に焦点を当てます 。文書では、以下の形式が推奨されています。
- プロンプト: 「<課題を記入>という困りごとは、長年多くの人が困っているにもかかわらず、解決されないままでいました。これらの問題の解決を阻害する要因は何でしょうか。」
- ポイント: 「本人の意志が弱いから」や「能力不足」といった言葉は使わずに、AIに問題の「根っこ」を探してもらいましょう 。
- 結果を分析する: AIは、解決を妨げている「根っこ」の問題を可能な限り多く列挙してくれます 。その中から最も深い部分にある問題を見つけ、それを解決していくと、元の問題が解決可能なものに変わっていきます 。
具体例:英語学習を妨げる要因を探る 🗣️
文書には、この方法をどのように使うかの完璧な例が示されています。
| 課題 | AIへの質問(プロンプト) |
| 大人になってから英語を勉強しても上達が遅い 。 | (大人になってから英語を勉強しても上達が遅い)という困りごとは、長年多くの人が困っているにもかかわらず、解決さないままでいました。これらの問題の解決を阻害する要因は何でしょうか 。 |
なぜこの方法が有効か: この質問をすることで、AIは「もっと勉強しなさい」のような一般的な答えを出すのではなく、モチベーションの欠如や忙しいスケジュールといった、個人が抱える心理的・外的要因を分析し、より具体的で役に立つヒントを与えてくれるのです 。
AIは、人間側の「使い方」によって「使えるかどうか」が決まります 。どのように質問するかを工夫することで、AIからより質の高い回答を引き出し、思考の質を飛躍的に向上させることができます 。
次は以上の考え方に基づき、私がAIに中小企業経営に係る課題から、阻害要因を分析し、課題解決の方向性を導き出した例です。
【具体例】中小企業の経営についてのプロンプトと回答例
プロンプト1
<人件費高騰、原価アップという状況の中、倒産件数を大幅に増えています。このような中、中小企業経営者はどういう経営を進めるべきか>という困りごとは、現在多くの人が困っているにもかかわらず、解決されていません。これらの問題の解決を阻害する要因は何でしょうか。
回答
この課題の解決を阻害する要因は、以下のような点が挙げられます。
抜本的なイノベーションの欠如:
多くの経営者は、人件費や原材料費の高騰をコスト削減や価格転嫁で乗り切ろうとします。しかし、これは一時的な対症療法に過ぎません。根本的な解決には、事業モデルの見直しや生産プロセスの抜本的な改革といった、より大きなイノベーションが必要です。しかし、これには多大な時間、資金、そしてリスクが伴うため、多くの企業が挑戦できずにいます。
マインドセットの問題
- 過去の成功体験への固執: 過去の成功体験から脱却できず、「これまでやってきた方法を変える必要はない」と考える経営者が少なくありません。新しい技術や市場の変化に対応できず、時代遅れの経営戦略に陥ってしまいます。
- リスク許容度の低さ: 中小企業は、大企業に比べて経営基盤が弱いため、大きなリスクを冒すことに慎重になりがちです。新しい投資や事業転換に踏み切れず、現状維持を優先してしまいます。これが、競争力の低下を招く大きな原因となっています。
外部環境の変化への適応力不足
- 情報収集と分析の遅れ: 市場の動向、技術の進化、競合の動きなど、外部環境の変化に関する情報収集が遅れがちです。客観的なデータに基づいた経営判断ができず、勘や経験に頼った経営に終始してしまいます。
- 人材の確保と育成の困難さ: 変化に対応できる優秀な人材を確保し、育成することが困難です。特に地方の中小企業では、賃金やキャリアパスの面で大企業に劣るため、優秀な人材が集まりにくいという構造的な問題があります。
資金調達の難しさ
- 金融機関の評価基準: 多くの金融機関は、中小企業への融資において、過去の実績や担保を重視します。将来性やイノベーションへの挑戦を正当に評価してもらえないことが多いため、新しい取り組みのための資金調達が難しくなります。
これらの要因が複合的に絡み合い、中小企業が人件費や原材料費の高騰という困難な状況を乗り越え、持続的に成長することを阻害しているのです。
プロンプト2
もっとも解決すべき本質的な要素はなんでしょう。
回答
前回お話ししたように、中小企業が直面する課題は複合的であり、その中で「最も解決すべき本質的な要素」は、おかれた状況によって異なります。
一般的に、多くの経営者にとって最も根深い問題は**「マインドセット」**に起因することが多いです。特に、以下のような点が挙げられます。
- 過去の成功体験への固執: 過去のやり方で成功した経験が、新しい変化への対応を妨げていませんか?
- リスク許容度の低さ: 新しい事業や技術への投資を躊躇し、現状維持に終始していませんか?
もし、あなたがこのマインドセットの問題を乗り越えることができれば、次に挙げた他の課題(イノベーションの欠如、外部環境への適応力不足、資金調達の難しさ)も、解決への糸口が見えてくる可能性が高いです。
ご自身の状況を振り返って、この中で「これこそが最も自分にとっての課題だ」と感じるものはありますか?その要素を特定できれば、より具体的な解決策を一緒に考えることができます。
プロンプト3
リスク許容度の低さです。
回答
リスク許容度が低いことが、本質的な課題であるとご認識されたのですね。この問題の解決を阻害している根本的な要因は、多くの場合、以下の3つに集約されます。
1. 「失敗」の定義が間違っている
多くの経営者は、新しい試みがうまくいかなかったことを「失敗」と捉えます。しかし、本当の失敗とは、**「何も学ばずに終わってしまうこと」**です。新しい挑戦は、結果がどうあれ、必ず何らかのデータ、知見、経験という貴重な「学び」をもたらします。この学びを次の事業に活かせば、それは失敗ではなく、未来への投資となります。この考え方にシフトしない限り、リスクを取ることは困難です。
2. 完璧主義と過剰な準備
完璧な計画や、失敗する可能性をゼロにするまで準備しようとすることで、結局何も行動を起こせない状態に陥ります。中小企業が直面する市場は変化が速く、**「行動しながら修正する」**アプローチこそが最も効果的です。大きな初期投資を避け、まずは小さく試して、市場の反応を見ながら改善していく「リーンスタートアップ」のような考え方を取り入れることが、リスクをコントロールする上で非常に重要となります。
3. 情報不足による恐怖
リスクが未知数なのは、必要な情報や知識が不足しているからです。新しい技術や市場、競合の動向について、客観的なデータに基づいた分析ができていないと、漠然とした恐怖感が先行してしまいます。この恐怖を乗り越えるためには、まず外部環境の変化を正確に把握するための情報収集を徹底し、可能なリスクとリターンを冷静に評価する姿勢を持つことが不可欠です。
これらの要因を乗り越えることができれば、リスクを「回避すべきもの」ではなく、「管理すべきもの」として捉えられるようになります。
あなたが抱えている「リスク許容度の低さ」は、これらのうちどの要因が最も強く影響していると感じますか?
プロンプト4
完璧主義と過剰な準備
回答
この完璧主義と過剰な準備こそが、リスクを過剰に恐れてしまう真の原因なのですね。
「なぜ完璧を求めるのか」を掘り下げる
この問題の根底にあるのは、多くの場合、**「失敗への恐怖」**です。
- 対面する現実から目を背けている: 完璧に準備している限り、「まだ本番ではない」「まだ失敗していない」という感覚でいられます。これは、不確実な未来や失敗する可能性という現実から目を逸らし、心理的な安心を保とうとする無意識の防衛機制です。
- 計画を立てることで「やった気になる」: 多くの時間を費やして完璧な計画を立てることで、実際にアクションを起こさなくても、あたかも事業を進めているかのような感覚に陥ることがあります。これは、行動の代わりに行動の計画を立てるという悪循環を生み出します。
- 他者からの評価を過度に気にしている: 「失敗したら、周りからどう思われるだろうか」という恐れも、完璧主義を加速させる一因です。特に中小企業の経営者は、社内外から常に注目される立場にあり、完璧な姿を見せたいというプレッシャーを感じやすいのです。
これらの要因を放置したままだと、どんなに良いアイデアや機会があっても、一歩も前に進めない「思考停止状態」に陥ってしまいます。
「小さく始めて、すぐに動く」ための具体的なステップ
この悪循環から抜け出すためには、まず**「完璧ではないこと」を受け入れる**ことから始めましょう。そして、以下のステップを試してみてください。
- 最小限の実行可能な計画を立てる: いきなり大規模な投資や事業転換を考えず、まずは**「今週中にできること」**といった、ごく小さな目標を設定します。
- 実行し、市場の反応を見る: 完璧な準備を待たず、とにかくその小さな計画を実行に移します。重要なのは、その結果が成功か失敗かではなく、顧客や市場からどのような反応が得られたかです。
- フィードバックから学ぶ: 得られた反応を分析し、次のアクションに活かします。この「実行→フィードバック→改善」のサイクルを高速で回すことで、過剰な準備が不要な「行動の習慣」が身につきます。
このプロセスを繰り返すことで、リスクは回避すべきものではなく、**「学びを得るための機会」**へと変わっていきます。
この中で、あなたが最も抵抗を感じるステップはどれでしょうか?
プロンプト5
実行し、市場の反応を見る
回答
過剰な準備よりも、「実行し、市場の反応を見る」ことに抵抗を感じるのですね。これは、**「不確実性」と「責任」**への恐怖が根底にあるからです。
不確実性への恐怖
- 予測不能な結果への不安: 完璧に準備できない状態で行動すると、結果がどうなるか予測できません。この不確実性が、失敗への恐怖を増幅させます。多くの経営者は、**「計画通りに進まないこと」**そのものをリスクだと考えがちです。
- 現状維持バイアス: 新しい行動を起こすことで、たとえ現状が困難であっても、慣れ親しんだ状態(コンフォートゾーン)から抜け出すことになります。人間は変化を嫌う傾向があるため、無意識のうちに現状を維持することを選択してしまいます。
責任への恐怖
- 失敗の「責任」を負うこと: 準備が不十分な状態で行動し、もし失敗した場合、その責任はすべて自分にあると感じてしまいます。この責任の重さが、行動をためらわせる大きな要因です。
- 「無能」と見られることへの恐れ: 失敗は、経営者としての能力がないと見なされるのではないかという恐怖につながります。特に、従業員や取引先に対して「完璧な経営者」でありたいという気持ちが強い場合、このプレッシャーはさらに増します。
「小さく始める」ための第一歩
この「行動への抵抗」を乗り越えるためには、まず**「失敗」の捉え方を変える必要があります。失敗は、「未来の成功に必要なデータ」**と定義し直しましょう。その上で、以下の問いかけを自分自身にしてみてください。
- 「もし失敗しても、失うものは何だろうか?」: 経済的な損失、時間、評判などを具体的にリストアップしてみてください。多くの場合、想像しているほど大きなものではないことに気づくはずです。
- 「この行動から、どんな学びが得られるだろうか?」: たとえ事業がうまくいかなくても、顧客のニーズ、市場の動向、新しい技術の知見など、必ず何らかの貴重な情報が手に入ります。
これらの問いを通じて、「失敗」が単なる損失ではなく、**「学び」であり「将来への投資」**であると認識が変われば、行動への抵抗感は和らいでいくはずです。