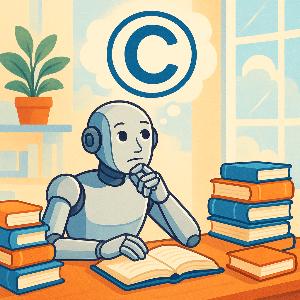以下の音声はGoogle AIスタジオで作成した[テキスト→音声ファイル変換アプリ」で生成したものです。再生スピードを変えたい場合は右側の3点リーダー「︙」をクリックし調整してください。
1. はじめに:AIと著作権を巡る議論の現在地
生成AIの技術は目覚ましい発展を遂げ、私たちの創作活動やビジネスに新たな可能性をもたらす一方で、その急速な普及は、著作権を巡る新たな課題を浮き彫りにしています。クリエイターは自身の作品が無断で学習・利用されることへの懸念を抱き、AI開発者は意図せず著作権を侵害するリスクに直面し、そしてAI利用者は生成したコンテンツが誰かの権利を侵害しないか不安を感じています。
こうした各方面からの懸念に応えるため、文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、2024年3月15日に**『AIと著作権に関する考え方について』**(以下、「本考え方」)を公表しました。これは、AIと著作権の問題に関する現時点での法解釈の指針を示す、非常に重要な文書です。ただし、この文書自体に法的な拘束力はなく、あくまで現時点での「考え方」を示すものです。今後、具体的な裁判例の蓄積や技術のさらなる進展、諸外国の動向に応じて、内容は見直されていく可能性があります。
このガイド解説は、「本考え方」の要点をステークホルダー(クリエイター、開発者、利用者)ごとに分かりやすく整理し、解説するものです。各当事者が自らの活動に伴う法的リスクを自己評価し、自身の権利を正しく理解するための一助となることを目指します。
本ガイドを読み進めるにあたり、まずはAIという新たな「道具」を巡る議論の土台となる、日本の著作権法の基本原則から理解を深めていきましょう。
2. 検討の前提:AI時代の羅針盤となる著作権法の4つの基本原則
AIと著作権の問題を正しく理解するためには、特定のAI技術の仕組みだけでなく、その判断の基盤となる日本の著作権法の基本理念を把握することが不可欠です。本考え方では、AIはあくまで人間が用いる高度な「道具」であり、その利用に伴う責任は原則として人間に帰属するという**「人間中心の原則」**を大前提としています。
この原則のもと、AI時代の法的問題を分析するための羅針盤となる、以下の4つの基本原則を確認します。
- 保護される著作物の範囲(表現・アイデア二分論) 著作権法が保護するのは、思想や感情が創作的に**「表現」されたものであり、その根底にある「アイデア」や「作風」**そのものではありません。例えば、特定の画家の「力強い筆致」や「独特の色使い」といった作風(アイデア)を模倣しただけでは、直ちに著作権侵害とはなりません。この原則が、AIによる作風の模倣がどこまで許されるのか、という議論の出発点となります。
- 保護される利益(支分権の考え方) 著作権は、著作物のあらゆる利用を独占できる万能の権利ではありません。法律は、複製権(コピーする権利)や公衆送信権(インターネットで送信する権利)など、特定の利用形態(法定利用行為)を**「支分権」**として定めており、権利者の保護はこの範囲に限られます。著作物を単に閲覧・鑑賞したり、記憶したりする行為は、これらの支分権に該当しないため、権利者の許諾は不要です。
- 権利制限規定の考え方 文化の発展という目的のため、著作権法は、著作物の公正な利用を図る例外規定を設けています。これが**「権利制限規定」であり、特定の条件下では権利者の許諾なく著作物を利用できます。後述する著作権法第30条の4**(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)は、AI開発におけるデータ学習の適法性を判断する上で中心的な役割を果たす、極めて重要な規定です。
- 我が国の著作権法が適用される範囲(準拠法) AIサービスは国境を越えて利用されるため、どの国の著作権法が適用されるかが問題となります。著作権侵害に基づく損害賠償請求では原則として**「結果発生地法」(侵害の結果が発生した国の法律)が、差止請求では「保護国法」**(権利保護が求められる国の法律)が適用されると考えられています。具体的には、以下のような事情がある場合、日本の著作権法が適用される可能性が高まります。
- AI学習のためのデータ収集プログラムが日本国内のサーバーで稼働している。
- 生成AIが日本国内のサーバーで稼働している。
- AIサービスが、日本国内のユーザーに向けて生成物を公衆送信している。
- 日本国内の端末から複製等の指令が入力された、または利用者が日本国内に所在している。(※脚注13に基づく見解)
- 要するに、AIサービスが日本市場をターゲットにしている、あるいは日本国内のサーバーで運用されている場合、事業者の所在地に関わらず、日本の著作権法を遵守する必要性が高いと言えます。
これらの基本原則は、AIが関わる各段階、すなわち「開発・学習段階」と「生成・利用段階」における具体的な著作権問題を分析するための基礎となります。次章では、まずAI開発の核心である「開発・学習段階」の論点を掘り下げます。
3. 【開発・学習段階】AIは著作物を無断で学習できるのか?
AI開発の根幹をなす「機械学習」において、既存の著作物を含む膨大なデータをどのように扱うかは、AIと著作権を巡る最大の論点の一つです。この適法性を判断する鍵となるのが、**著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)**です。本章では、この規定の解釈を中心に、AI開発・学習段階の法的問題を深掘りします。
AIの開発・学習プロセスにおいて、既存著作物の「複製」が生じうる具体的な場面には、以下のようなものが挙げられます。
- AI学習用データセット構築のための学習データの収集・加工
- 基盤モデル作成に向けた事前学習
- 既存の学習済みモデルに対する追加的な学習(ファインチューニング等)
- 検索拡張生成(RAG)等で用いるデータベースの作成
3.1. 原則:「享受」を目的としない利用(法第30条の4)
著作権法第30条の4は、AI開発のための情報解析のように、著作物に表現された思想や感情を**「享受」**(作品を鑑賞して味わい楽しむこと)する目的ではない利用を、原則として権利者の許諾なく適法とする、柔軟な権利制限規定です。
この立法趣旨は、情報解析のような利用は、作品の価値を直接享受して知的・精神的欲求を満たすものではないため、著作権者が本来得るべき対価回収の機会を損なわず、その利益を通常害さないという考えに基づいています。これにより、イノベーション創出を促進することが目指されています。
3.2. 例外①:「享受」目的が併存する場合
法第30条の4が適用されない重要な例外の一つが、情報解析などの主目的に加えて**「享受」目的が併存する**と評価される場合です。たとえ主目的が情報解析であっても、同時に享受目的が含まれていれば、この規定の対象外となります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 事例1:特定の著作物の表現を出力させる意図的な学習
- 特定の作品の表現を意図的に再現させるための**「過学習(overfitting)」**を行う場合。
- 特定のクリエイターの作品群のみを追加学習(ファインチューニング等)させ、その創作的な表現そのものをAIに出力させることを目的とする場合。
- 事例2:検索拡張生成(RAG)等での表現の出力目的
- RAGのような技術において、そのシステムが単にデータベースから事実を要約するためでなく、データベース内の著作物の創作的表現そのものを意図的に検索・取得し、回答として出力することを主目的として設計されている場合。この場合、目的が単なる情報解析から「享受」へと移行したと評価される可能性があります。
3.3. 例外②:「著作権者の利益を不当に害する場合」(ただし書)
法第30条の4にはもう一つの重要な例外として、**「ただし書」**が存在します。これは、たとえ享受目的でなくても、「著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、適用が除外されるというものです。これは、既存の著作物の利用市場と衝突したり、将来の潜在的な販路を阻害したりする場合を想定しています。
a) 情報解析用のデータベース市場と競合する場合
大量の情報を情報解析しやすい形で整理した「データベースの著作物」が有償で販売されているにもかかわらず、そのデータベースを無断で複製してAI学習に利用する行為は、著作権者の市場と直接競合するため、利益を不当に害すると考えられます。 具体例: 有償のAPIを提供している学術論文サイトや新聞社のサイトから、APIを利用せずにクローラー等でデータを収集し、AI学習に用いる行為。 逆に言えば、本考え方は、ウェブサイトがrobots.txtのような技術的措置でクローラをブロックしていない場合、権利者が現時点でそのコンテンツを情報解析用の商用データベースとして扱っていないと推認され、市場への不利益を主張する根拠が弱まる可能性を示唆しています。
b) 技術的措置を回避して複製する場合
権利者が、ウェブサイトにおいてrobots.txtなどを用いてAI学習用クローラのアクセスを拒否する技術的な措置を講じている場合があります。このような措置が、将来的に情報解析用のデータセットを有償で販売する市場を確保するためであると推認される場合、その措置を意図的に回避してデータを収集する行為は、著作権者の将来の潜在的販路を阻害するものとして「利益を不当に害する」と評価され、法第30条の4の適用外となる可能性があります。
3.4. 論点:海賊版サイトからのデータ学習
海賊版と知りながら、そのコンテンツをAIの学習データとして収集・利用する行為は、極めて慎重に判断されるべき問題です。
「本考え方」によれば、この行為自体が直ちに法第30条の4の適用を否定するものではないとされています。しかし、それによって開発されたAIが将来的に著作権侵害を引き起こした場合、開発事業者が**「規範的な行為主体」**(侵害行為を直接行っていなくても、状況への支配や影響力から法的な責任を問われうる当事者)として責任を問われる可能性を高める一要素となり得ると指摘されています。
この「規範的な行為主体」という概念は極めて重要です。なぜなら、開発・学習段階での意思決定(例:海賊版データの利用)が、生成・利用段階で発生した著作権侵害の法的責任に直接結びつく可能性を示しているからです。特に、侵害発生の蓋然性を認識しながら結果を回避する措置を講じなかった場合、その責任はより重くなると考えられます。
——————————————————————————–
開発・学習段階における適法性の議論は、主に法第30条の4の解釈を巡って展開されます。しかし、これらの学習済みモデルを用いて実際にコンテンツを生成・利用する段階では、全く異なる法的論点が浮上します。
4. 【生成・利用段階】AI生成物は著作権侵害になるのか?
AIを用いてコンテンツを生成し、それを公開・利用する行為は、AI利用者にとって最も身近な法的リスクが伴う段階です。AI生成物が既存の著作物の著作権を侵害するか否かは、従来の判例法理と同様に、**「類似性」と「依拠性」**という2つの要件が両方認められるかによって判断されます。
4.1. 要件①:類似性(表現上の本質的な特徴の感得)
AI生成物と既存の著作物の間に「類似性」があるかどうかは、単にアイデアや画風、作風が似ているだけでは判断されません。重要な基準は、AI生成物から**「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる」**かどうかです。つまり、誰が見ても「あの作品の表現を真似ている」と認識できるレベルの具体的な表現の一致が求められます。
4.2. 要件②:依拠性(既存の著作物へのアクセス)
「依拠性」とは、既存の著作物を知った上でそれに基づいて創作したことを指します。AIの利用においては、この判断が特に複雑になります。AI利用者が既存の著作物を知っていたかどうかが重要なポイントとなり、主に以下の3つのケースに分けて考えられます。
- ケース1:AI利用者が既存の著作物を認識していた場合
Image to Image機能で既存の作品画像を入力したり、「〇〇(特定の作品名)風に」といったプロンプトを入力したりして、意図的に類似したものを生成させた場合、利用者は既存の著作物に依拠したと判断され、依拠性は明確に認められます。 - ケース2:AI利用者は認識していなかったが、AIがその著作物を学習していた場合 利用者がその著作物の存在を知らなくても、AIが開発段階でその著作物を学習データとしてアクセスしているため、客観的にはアクセスがあったと見なされます。このシナリオでは、法律は一般的に利用者が元作品に依拠したと「推認」します。つまり、意図していなくても依拠があったと推定され、立証責任は「これは偶然の一致である」と主張する利用者側に転換されるため、反証は非常に困難になる可能性があります。立証責任(証明する義務)が利用者側に移るのです。でも、AIの学習データなんて全部調べられませんから、「偶然の一致です!」と証明するのは現実的にはとても難しい。
- ケース3:AI利用者も認識しておらず、AIも学習していなかった場合 利用者もAIも既存の著作物にアクセスしていない状況で、偶然に類似したものが生成された場合は**「偶然の一致」**と見なされます。このケースでは依拠性が否定されるため、著作権侵害は成立しません。
【実践的ポイント】依拠性を巡る各ステークホルダーの視点
利用者にとって: 最も重要な点は、「元になった作品を知らなかった」という主張が、使用したAIがその作品を学習していた場合には有効な防御策にならない可能性が高いということです。これにより、意図しない著作権侵害のリスクが生まれます。
開発者にとって: 開発したモデルの学習データが、AI利用者の生成物と元作品との間に法的な繋がり(依拠性)を生み出します。学習データの透明性を確保したり、特定の著作物の表現を再現しないようなフィルタリング技術を導入したりすることが、重要なリスク管理策となり得ます。
4.3. 責任の所在:誰が責任を負うのか?
AIによる著作権侵害が発生した場合、誰がその責任を負うのでしょうか。
原則として、生成という物理的な行為を行った**「AI利用者」**が責任を負います。
しかし、特定の条件下では、**「AI開発事業者」や「AIサービス提供事業者」も「規範的な行為主体」**として責任を問われる可能性があります。事業者が責任を問われる可能性が高まる状況としては、以下のようなものが挙げられます。
- 特定のAIを用いると、著作権侵害物が高頻度で生成される場合。
- 事業者が、AIが既存著作物の類似物を生成する蓋然性が高いと認識しながら、それを抑制する措置を講じていない場合。
——————————————————————————–
生成・利用段階での著作権侵害リスクを理解した上で、次に視点を変えてみましょう。AIが生成したアウトプットそのものが、そもそも「著作物」として法的に保護されるのか。これは、クリエイターや事業者にとって極めて重要な論点です。
5. 【生成物の著作物性】AIが作ったものは誰のものか?
生成AIを活用してコンテンツを制作し、ビジネス展開する上で、その生成物が著作権法で保護される「著作物」に該当するかどうかは、権利保護やライセンス契約の観点から極めて重要です。
結論から言えば、AI自体は著作者にはなれません。AI生成物が著作物として認められるかどうかは、その生成プロセスにおける人間による**「創作的寄与」の有無が判断の鍵となります。具体的には、人間の「創作意図」と、その意図を実現するための具体的な「創作的寄与」**が認められる必要があります。
単に漠然としたアイデアを指示したり、ありふれた指示を与えたりしただけでは、創作的寄与とは見なされにくく、生成物の著作物性が否定される可能性が高まります。 「本考え方」は、この判断に影響を与える複数の要素を概説しています。以下の表は、その趣旨に沿った実践的な例と共に、これらの要素をまとめたものです。
| 判断要素 | 創作的寄与が認められる可能性を高める行為 | 創作的寄与とは見なされにくい行為 |
| 指示・入力 | 創作的表現を具体的に示す詳細な指示(構図、色彩、人物の表情など、表現を細かくコントロールするプロンプト) | アイデアレベルの漠然とした指示(例:「美しい風景」) |
| 試行錯誤 | 生成結果を確認し、意図する表現になるよう指示を何度も修正・追加しながら試行を繰り返すこと | 単に多くの生成を試みただけで、指示内容に工夫がないこと |
| 選択・修正 | 複数の生成物から特定のものを選択し、さらに自身の創作性を加えるため加筆・修正を行い、独自の創作的表現を付与すること | 単に自動生成された複数の候補から一つを選ぶだけの行為 |
もしAI生成物に著作物性が認められなかった場合でも、他者がそれを無断で複製・利用する行為が、営業上の利益を侵害するなどの特段の事情があれば、民法上の不法行為として、一定の法的保護が与えられる可能性は残されています。
——————————————————————————–
AI生成物の権利関係を整理したところで、最後に本レポート全体のまとめと、今後の議論の行方について展望します。
6. まとめと今後の展望
本レポートで解説した『AIと著作権に関する考え方』は、複雑化するAIと著作権の問題を理解するための羅針盤です。その核心的なポイントは、以下の3つの段階に集約されます。
- 開発・学習段階 原則として著作権法第30条の4により適法だが、「享受目的の併存」や「著作権者の利益を不当に害する」といった例外的な場合には違法となる可能性がある。
- 生成・利用段階 従来の著作権侵害と同様に「類似性」と「依拠性」が揃えば侵害となる。特に、AIが過去に著作物を学習していた場合、利用者がその事実を知らなくても依拠性が推認され得る点に注意が必要。
- 生成物の著作物性 AIは著作者になれず、人間の「創作的寄与」が十分に認められれば、その人間を著作者とする著作物となり得る。ただし、その判断は個別具体的なケースによる。
AIと著作権を巡る議論はまだ発展途上にあります。「本考え方」も、今後の国内外の判例の蓄積、技術の進展、国際的なルール形成の動向によって、今後見直され、更新されていくことが想定されています。
クリエイター、開発者、利用者の各当事者は、政府が示す考え方を理解し、法的リスクを適切に管理することが求められます。それと同時に、当事者間での対話を進め、実態に即した利用ルールやガイドラインを自主的に策定していく努力もまた、健全な創作エコシステムを維持・発展させる上で不可欠と言えるでしょう。
(参考)以上を踏まえた対応策を追加します。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| ① 使用するAIの出所を確認 | 「著作権クリア済み」「商用利用OK」と明記されたAIを選ぶ |
| ② 出力をそのまま使わない | AIの出力をリライト・編集・検証してオリジナリティを加える |
| ③ 商用利用時は確認 | ロゴ・画像・文章・音楽などを使う前に著作権侵害チェック |
| ④ 契約書・利用規約の確認 | AIサービス提供者との契約で責任範囲を明確にしておく |
| ⑤ 社内ルール整備 | 「AI生成物を使うときのルール」を就業規則・ガイドライン化する |